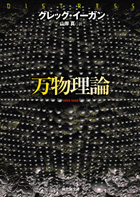 豪快で意表を突く奇想。論理のアクロバットとも呼ばれるほど大胆にして、偏執的なまでに緻密なロジック展開。
豪快で意表を突く奇想。論理のアクロバットとも呼ばれるほど大胆にして、偏執的なまでに緻密なロジック展開。
それが混然となって、グレッグ・イーガンの長篇は読者に壮大なめまいを引きおこす。そのめまいこそは、《F&SF》誌で本書を書評したロバート・K・J・キルヘファーのいう“圧倒的な知的スリル”――SFの魅力にとりつかれたころはつねに感じていた、ほかでは味わえない興奮――にほかならない。
さらに、惜しげもなく投入された長篇数冊分のアイデアが、そのめまいに輪をかける。
『宇宙消失』(創元SF文庫)や『順列都市』(ハヤカワ文庫SF)で多くの読者を熱狂させたこうした特徴は、現時点での作者最長の作品(『宇宙消失』の5割強増し)である本書にも、もちろん共通する。イーガンの長編は1冊ごとにタイプが違うので、面白さを比較しても意味はないのだが、あえてどれがいちばんの傑作かといわれれば、個人的には本書だと思う。
以下、読みどころのいくつかを中心に本書の内容を追いつつ、若干の解説を加えていきたい――のだけれど、最大の読みどころであるメインの奇想、肝心のSF的大ネタがどんなものかは、当然ながらバラすわけにいかない。また、その大ネタにつけられた造語(『順列都市』での“塵理論”のような)も、ストーリーの関係でここには書けないのである。ただ、作者が本書を、『宇宙消失』や『順列都市』と並んで“主観的宇宙論もの”と呼んでいることは、(本書刊行前のインタビュウでの発言でもあることだし)書いておいていいだろう。つまりこれは前の2長篇同様、宇宙の秘密についての物語なのだ。
その大ネタと密接に絡むのが、邦題になっている万物理論(Theory of Everything の頭文字をとって、作中ではTOEと略されることが多い)。とはいえ万物理論自体はイーガンの奇想でも造語でもなく、現実に研究がおこなわれているものだ。たとえばサイエンス・ライターのJ・D・バローに、ずばり『万物理論』(みすず書房)という著作があり、この訳書のカバー裏から引けば、万物理論とは「あらゆる自然法則を包み込む単一の描象」、「物理的実在の根底にある論理」ということになる。本書第11章の前半でも同様のことが、より踏みこんで語られているが、現実の研究や議論については、本書末尾の「作者より」にあがっているワインバーグの『究極理論への夢』などを参考にしていただきたい。
本書の舞台となる2055年、その“夢”の理論が完成寸前になっていた。アインシュタイン没後百周年記念の国際理論物理学会議の席上で、3人の学者がそれぞれに異なる理論を発表する予定になっていて、もちろん正しいのはどれかひとつだけ。3人の理論の中で、万物理論の最有力候補と目されているのが、まだ20代のノーベル賞受賞者ヴァイオレット・モサラという女性のものだった。
主人公アンドルー・ワースは、バイオテクノロジーに精通した科学ジャーナリストで、《シーネット》という世界規模の放送局(テレビとコンピュータ・ネットの性格をともにもっている)の専属で番組を製作している。モサラを軸に万物理論をあつかう番組を作ることになったワースは、会議がひらかれる南太平洋の人工の島、ステートレスにむかう。だが、そこで彼は次々と予期せぬ事態に遭遇し、命の危険にすらさらされることに……。
というストーリーが展開されるのは、第2部にはいってから。第1部では、ワースが約一年がかりで取材してきた『ジャンクDNA』という番組を、シドニー郊外の自宅で編集する過程を通して、2055年のテクノロジー世界がスケッチされていく。そこで披露されるアイデアの数々がこのパートの読みどころ(その意味では『宇宙消失』の第1部と通じる)。そもそもワース自身が、視神経にチップを直結して“見たまま”の映像を撮影できたり、仕事が修羅場になるとホルモンを制御して睡魔を遠ざけたり(心底うらやましい!)という、時代の申し子なのである。
そんな彼も、『ジャンクDNA』用に取材した4つの事例には、トラウマになりそうな衝撃を感じていた。それはいずれも、人の生死/人類という種(しゆ)/余命/人間性といったものの定義をバイオテクノロジーの力で平然と崩そうとする、フランケンサイエンスと蔑称されるたぐいのものだったからだ。たとえば第1章でワースが取材する“死後復活”は、殺人事件の被害者の生命活動を臨終直後に短時間復活させて、犯人の名前をききだそうというもの。そんなショッキングで悪夢めいた事例とばかり接しつづけた彼は耐えがたくなって、思わず畑違いの万物理論の番組作成に名乗りをあげてしまうのだった。
ところで、第1章の死後復活もそうだが、本書では『ジャンクDNA』のほかの事例や、全篇に出てくるそれ以外のさまざまなテクノロジーも、別に伏線というわけでもないのに微にいり細をうがって説明されている。それはイーガンのほかの作品でも見られることだが、本書にはその理由を語ったくだりがある。第4章でアーサー・C・クラークの第3法則(『じゅうぶんに発達したテクノロジーは魔法と区別がつかない』)に言及した部分がそれで、人間の生んだテクノロジーを人々が魔法あつかいしないようにするのが科学ジャーナリストの使命だ、と主人公はいう。詳細な説明は、いわばその実践なのだ。
(そういう主人公も、物理学には門外漢であるわけで、だから読者は、本書のその方面の記述に理解できないところがあっても、気にせずに読み進めばいいのである……というのはまあ半分冗談だが)
この“使命”は、科学やテクノロジーに対するイーガンのスタンスでもあるといっていいだろう。このほかにも、本書では作者の科学観、人間観、社会観などがいたるところで語られ、それを抜きだしていけばイーガン論ができそうなほどだ。
(2004年10月10日)
|