ミステリの歴史を考えるうえで、第一次世界大戦の終わった1918年から第二次世界大戦が始まるころまでを、黄金時代と呼ぶことがあります。これは正しくは謎解き長編小説の黄金時代と称するべきで、確かにエラリー・クイーンにアガサ・クリスティ、ディクスン・カー、アントニイ・バークリー、ドロシー・L・セイヤーズ、F・W・クロフツ……この時期に登場した大物作家を数えあげていくだけで、溜め息が出ます。しかし、それにつづく、1940年代を中心とするアメリカ探偵小説の愉しさだって格別ではないでしょうか。クレイグ・ライス、レイモンド・チャンドラー、ウィリアム・アイリッシュ……都会を舞台に洗練された味わいの物語をうみだした彼らが、ミステリの愉しさをおしひろげたことは疑うべくもありません。
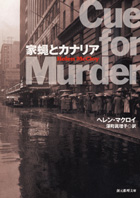 さて、そこで『家蠅とカナリア』です。
さて、そこで『家蠅とカナリア』です。
ヘレン・マクロイの長編第五作。1938年にデビューして以来、精神分析学者の名探偵ベイジル・ウィリング博士を主役に謎解き小説を書きついできたマクロイの、これは初期の総決算という呼び声も高い傑作です。巻頭に収録したアンソニー・バウチャーの序文をひいてみましょう。
わたしの知るかぎりのもっとも精緻な、もっとも入り組んだ手がかりをちりばめた探偵小説のひとつ……この解決に驚くなかれと言うことにより、ひとは、驚くなかれ、この作品をおおいに称揚することすら可能なのだ。手がかりの組み立てかたは、非常に細心かつ公正であるので、読者はドクター・ウィリングそのひととほぼ同じ時点で、答えを(当て推量ではなく)論理によって割りだせるはずである。さらに言えば、この作品に出てくるメスの柄にとまる蝿の問題、これはまさしく小説のなかで扱われたもっとも巧妙、かつもっとも想像力に富んだ手がかりのひとつだと言ってよい。
物語のはじめには“読者への挑戦状”とも受けとれる文章がおかれ、本書がエラリー・クイーンの国名シリーズにつらなるゲーム型の謎解き小説であることが宣言されます。大胆な手がかり、巧妙に張り巡らされた伏線、華やかな推論。愛好家には格好の贈り物でしょう。作者の挑戦に応じるもよし、素直に騙されて感嘆するもよし。謎解き小説ならではの愉しみを存分に味わってください。
ややこしいミステリは苦手だから……と尻込みしているかたはいらっしゃいませんか。ご心配なく。本書が発表されたのは1942年。そうです。“アメリカ探偵小説黄金時代”の刻印もまた、この小説には鮮やかに押されているのです。
主要な舞台はブロードウェイにほど近い劇場。その建物をつたえる手腕が、まず抜群です。ベイジル・ウィリングが開巻まもなく、非常階段をへて四階から劇場内に忍び入る場面があるのですが、その際の俯瞰の眼差しの魅惑的なことといったらどうでしょう。ベイジルの眼をとおして、豆粒のようなひとびとの動きが写しとられていくことで、単なる図面的な説明からは得られないこくを感じさせずにはおきません。マクロイはさらに、そこにさまざまな演劇人を躍動させます。観客の面前で不敵にも殺人をおこなった容疑をかけられる三人の役者はもちろん、脇役陣、演出家兼プロデューサー、衣裳デザイナー、戯曲家志願者などが、切れ味のある人物観察を得て、生きいきと動きだす。物語の途上で思いがけない素顔を明かすものもいれば、善人ぶりや悪人ぶりを全うするものもいます。その洗練された持ち味は、まさにこの時代の良き探偵小説ならではです。
純然たる犯人捜しの謎解き小説が、大衆小説としても実に精彩があって読みごたえがある――これは1940年代のアメリカに起こった小さな奇跡というべきかもしれません。時をへて、第二次世界大戦下のニューヨークを映した風俗小説としての興趣がくわわりましたし、演劇ミステリの白眉であるという点も見逃せません。読みどころ満載の名作を、どうか心ゆくまで味わってください。
 追記 ヘレン・マクロイはその後も、さまざまな物語をうみだしました。『ひとりで歩く女』は技巧を凝らした幻惑的な仕上がりの傑作で、恩田陸さんらに称賛されましたし、代表作として定評のある『暗い鏡の中に』(ハヤカワ・ミステリ文庫)は、千街晶之さんらが賛辞を贈る復刊の待たれる一冊です。また本書『家蠅とカナリア』にひきつづいて、11月には“人を殺す部屋”を扱った後期の代表作『割れたひづめ』が国書刊行会から、2003年早々にはバラエティ豊かな傑作短編集『歌うダイアモンド』が晶文社から、それぞれ刊行の運びとなると聞きます。変化に富むマクロイの小説世界を、一冊でも多くご堪能ください。
追記 ヘレン・マクロイはその後も、さまざまな物語をうみだしました。『ひとりで歩く女』は技巧を凝らした幻惑的な仕上がりの傑作で、恩田陸さんらに称賛されましたし、代表作として定評のある『暗い鏡の中に』(ハヤカワ・ミステリ文庫)は、千街晶之さんらが賛辞を贈る復刊の待たれる一冊です。また本書『家蠅とカナリア』にひきつづいて、11月には“人を殺す部屋”を扱った後期の代表作『割れたひづめ』が国書刊行会から、2003年早々にはバラエティ豊かな傑作短編集『歌うダイアモンド』が晶文社から、それぞれ刊行の運びとなると聞きます。変化に富むマクロイの小説世界を、一冊でも多くご堪能ください。
(2002年9月2日)
|